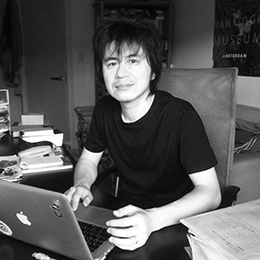グラスを傾けつつ嗜みたい、酒香るエッセイにして、ヒトとヒトサラ流のカルチャー・ガイド。ミュージシャンや小説家、BARの店主や映画人。街の粋人たちに「読むヒトサラ」をお願いしました。
グラスを傾けつつ嗜みたい、酒香るエッセイにして、ヒトとヒトサラ流のカルチャー・ガイド。ミュージシャンや小説家、BARの店主や映画人。街の粋人たちに「読むヒトサラ」をお願いしました。

 サイドオーダーズ26 / TEXT:桜井鈴茂 PHOTO:嗜好品LAB / 2016.7.29 この狂おしき世界の懐(ふところ)。呑むための、書くための──桜井鈴茂
サイドオーダーズ26 / TEXT:桜井鈴茂 PHOTO:嗜好品LAB / 2016.7.29 この狂おしき世界の懐(ふところ)。呑むための、書くための──桜井鈴茂
本欄のような、まあ、つまるところ、お酒との粋な付き合い方を紹介するコラム(そうですよね?)の執筆を二つ返事で引き受けておいてナンだが、ナンだがというか、まことに恐縮なのだが、おれはうまく酒が呑めない。酒はうまいと感じてはいる。酒が入らないと晩御飯も進まない。酒場や盛り場も総じて好きだ。それ以上に、酒なしでこのさき人生の荒波や不条理を乗り切っていけるとは思えない。しかし、告白する、告白させてほしい。おれはダメな酒呑みなんです。今夜はうまく/スマートに呑めたかも、と思える時もないではないが、打率はかなり低い。たいていは、その晩の寝しなに、またしても無粋な酒の呑み方をしてしまった、とさっそく後悔している。寝しなにそう思わなくても、翌朝には、脳内を這い回る自己嫌悪のナメクジに苛まれている。余計な愚痴をこぼしちゃったなあ、とか。あれはとんでもない暴言だった、とか。あの編集者からはもう仕事はもらえないだろうなあ、とか。また脱いじゃった、とか。つーかどうすんだよ今月の光熱費は、とか。それどころか、ここには書けない失態や粗相も数々。そんなこんなを翌朝うじうじと考え、ひどい時には死にたくなる。いやまあ、死にたくなるってのは大仰だけども、穴からは出たくない。穴とは正確に何を意味するのかわからないままに、もう二度と出たくないと思う。出なきゃ生きていけないから結局は出るんだけど。
スマートな酒呑み、とは決して言えない人でも、酒席での言動をうじうじと考えない人はいくらでもいる。だいいちそんなこまごまと覚えてねえよって人もたくさんいるだろう。おれはちがう。うじうじと考え抜くし、考え抜く材料となるあれこれをけっこう詳らかに覚えている。呑んでる時や帰り道ではほとんど気にかけていなかったあれこれが翌朝の起きしなに紛れもない失態や粗相として鮮やかに蘇る。どうやら、おれの場合、アルコールで壊滅するのは記憶ではないようだ。自制心のようだ。……最悪。
若い頃は……そうだな、しいて乱暴に区切れば33歳くらいまでは、違った……はずだ。めっぽうスマートな酒呑み、とは言えないにしても、マルガリータが注がれたカクテルグラスの脚に指先を伸ばしつつ、上方のスピーカーから粉雪のように降ってくるチャールズ・ミンガスに耳を傾け、前の晩に観たばかりのジョン・カサヴェテス映画について(自分ではそう思うところの)気の利いた寸評をぶち、おまけに話の合間に相手の女性の新しいヘアスタイルをさりげなく褒める、なんてこともできた……はずだ。まあ、少なくとも、その場に居合わせる人の気分を損ねないだけのたしなみはあった……んじゃないかと思う。というか、そもそも、アルコールの勢いを借りて吐き出さなくてはならない鬱憤なんて持ち合わせていなかったのかもしれない。あるいは、たとえなんらかの失態を演じても、翌朝それについてうじうじと考え抜いて穴から出たくなくなるなんてことはほとんどなかった。とっとと、手のひらと鼻頭を午前の陽光に晒し、その日以降を平然と生きていた。ベッドから這い出るのに、今日は残りの人生の最初の日、なんて言葉をわざわざ思い浮かべる必要はなかった。ああ、我が麗しき、かつ、おめでたき青春よ。
で、このへんからが本稿の主題になるのだが、無粋な、タチの悪い、少なくとも良くはない酒呑みに、零落したおれは、当然ながら、映画や音楽や小説の好みも変化してきた。もちろん、当時大好きで今も大好きなんてものもたくさんあるけど、当時はしびれていたのに今は全然しびれなくなったもの、あるいはその逆のものが、多々ある。繰り返すが、当然だ。べつに零落しなくても、当然だ。人は程度の差こそあれそんなふうに生きてゆく。今年の目標や信条をかえ、タバコの銘柄やログインパスワードをかえ、歯科医や愛猫や配偶者をかえ、無人島に持ってゆく10枚のアルバムや柩に入れてほしい10冊の本を入れかえ、生きてゆく。
ちょっと話が逸れた。小説の話に絞ろう。おれが今言いたいのは、お酒の呑み方が無粋になってゆくにつれ、どんな小説にしびれるか、小説のどんな場面にしびれるか、なんてことがはっきりと変わってきた、ということだ。小説における好みの変化は音楽や映画におけるそれよりも歴然としているように思う。どうしてそうなのかはともかく。今となってはいささか恥ずかしいけど、ずっと若い頃は、とくに酒場デビューしたばかりの頃は、村上春樹の小説に描かれる、男と男ないし男と女がバーボンソーダなんかを呑みながら交わす粋な会話に、しびれていた。正直に言おう、1985年のクリスマスのたしか前々日、想いを寄せていた長谷川裕美ちゃんを誘っておれはススキノのカフェ・バー(当時はその呼称が一般的だったはず)で1缶800円という当時の小遣いから捻出するには高価すぎるミケロブというアメリカのビールをちびちび舐めていたのだけど、裕美ちゃんが「11時までには帰らなくちゃ」と言いだした時に、おれが即座に返した「靴を忘れないようにね」というセリフは、氏の短篇「中国行きのスロウ・ボート」のワンシーンからのまんまパクリだ。しかも、自分のセリフにあまりにも酔っていて、裕美ちゃんがそれにどう応じたかはまるで覚えていない。「ああ、シンデレラね」と言ったとは思えないが。
何年か前に、「中国行きのスロウ・ボート」をはじめ、初期の村上作品をささっと読み直してみたのだが……なんだかねえ、だった。小説が悪いのではない。時代のせいも少しはあるのだろうけど、やっぱりおれ自身の問題だと思う。おれが零落して、小説空間のそこかしこに漂う「スマートさ」や「粋」にはどうあがいても手が届かなくなったのだ。そうして、なんだかねえと鼻白むことで、なけなしの矜持をどうにか保とうとしたのだろう。「スマートさ」や「粋」を手の届くものと感じるには、あまりにも我が情感やモラルは錆びつき、ロマンシチズムだかダンディズムだかは焦げつき、希望とパッションは爛れ、それどころか、絶望や諦念さえ水漏れしているのだ、きっと。なんて書くと気取ってるように思われるかもしれないが、ようするに、若かりし自分が眉をひそめていたはずの、だらしのない中年男になったということか。
などと書いてて、我ながら涙も出ないのに泣きそうになってきたが、泣く必要はない。泣くな、顔を上げろ。おれには(そして、あなたにも)ブコウスキーがいる。そう、チャールズ・ブコウスキー。LAの酔いどれ詩人。オールド・パンク。


ブコウスキーの小説作品はどれも自伝的要素が強いのだが、とりわけここで紹介したいのは、ようやく日の目を見た50代の放蕩の日々が記された長篇『詩人と女たち』。一言で言うなら、ぐだぐだ、である。ひたすら、ぐだぐだ、である。飲んではゲロを吐き、飲んでは社会を罵倒し、飲んでは売女じゃないけど売女みたいな女とファックし、二日酔いで目覚め、迎え酒を飲み、ゲロを吐き、ファックした女と罵り合い、別の女に会いに行って別のファックをし、競馬場へ出かけてはまた飲み、男友達とハッパをやりながらさらに飲み、たまに思い出したように詩を書いては飲み、朗読会に出かけていってはやっぱり飲み、飲み過ぎて呂律が回らなくなり、ブーイングを浴びるがそれでも飲み続け、直後のパーティで知り合った女とファックし、あるいはファックを試みるも酔いすぎて最後まではいけず、ごめんねと謝ってはまた飲み、二日酔いで目覚め、迎え酒を飲み、ゲロを吐いて……いったい何を書いてるんだがわからなくなってきたが、そんなのが延々と、文庫本にして500ページ以上にわたって繰り広げられる。ブコウスキーの分身である語り手チナスキーの言動もひどいが、小説自体もまたひどい。こんなのがよく出版されたよなあ、と思ってしまうほどにひどい。ひどすぎる。ひどすぎるのに、読み進めるうちにだんだんと高揚してくる。ヒュー!とか叫びたくなってる。おまけに目尻には涙まで滲んでる。ちなみにおれは原書まで買って読んだ。もしかしたら、素晴らしいってことなのかもしれない。傑作ってことなのかもしれない。稀にとてつもなく凄い名言を吐くが、その何倍かはしょーもないことをぶつくさ言ってる。そこがまたいい。すべってすべってすべりまくって稀にすべらないってのが。三振、併殺、三振、投ゴロ、稀に場外ホームラン。ぜんぜん粋じゃない。ちっともスマートじゃない。つーか、そんなものは歯牙にもかけていない。糞食らえってかんじ。すげえ。清々しい。豪傑だ。ダメな酒呑みの一人として言うなら、これほど「ま、いっか。今夜も飲んじゃお」と思わせてくれる小説はない。あるいは、小説家の端くれとして言うなら、技術的には何の参考にもならないにもかかわらずこれほど「おれもいっちょ、書いてみるか」という気にさせてくれる小説はない。ようするに、これほど元気が出る小説ってちょっとない。
もし、おれと同じようにあなたもタチの悪い酒呑みなら、無粋な酒呑みになりかけている自覚があるなら、ダメな酒呑みに堕してしまったかもと時にふさぎ込むことがあるなら、是非ともこの小説を読んでみてほしい。この狂おしき世界の懐は案外と深い。深くて豊かで、かなしくもおかしい。わたしやあなたが酒席で演じた失態や粗相も、たいていの場合、巡り巡って、誰かの酒の肴にはなっているものなのだ。
SIDE ORDERS :
・チャールズ・ブコウスキー『詩人と女たち』(1978)
・村上春樹『中国行きのスロウ・ボート』(1983)
・桜井鈴茂『どうしてこんなところに』(2014)
| 前の記事 ごえんがありますように ──江森丈晃 |
次の記事 彼女の部屋(スナックアーバンのこと) ──田尻彩子 |