あの店のヒトサラ。
ヒトサラをつくったヒト。
ヒトを支えるヒトビト。
食にまつわるドラマを伝える、味の楽園探訪紀。
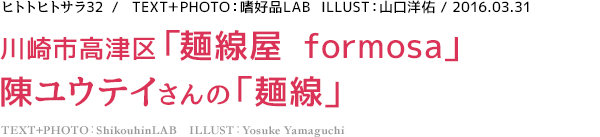 ヒトトヒトサラ32 / TEXT+PHOTO:嗜好品LAB ILLUST:山口洋佑 2016.03.31 川崎市高津区「麺線屋 formosa」陳ユウテイさんの「麺線」
ヒトトヒトサラ32 / TEXT+PHOTO:嗜好品LAB ILLUST:山口洋佑 2016.03.31 川崎市高津区「麺線屋 formosa」陳ユウテイさんの「麺線」
麺線(めんせん)。それは糸のようにきめ細かな麺を、トロトロと心地よい喉越しにて味わう台湾発祥のファストフード。幼少期を南部・屏東(へいとう)で過ごした陳ユウテイさんの記憶に留まり続けるソウルフードであり、このヒトサラを日本にも根づかせようとスタートさせた奮闘の場こそが、「麺線屋 formosa(フォルモサ)」である。
場所は田園都市線・二子新地駅から徒歩5分の住宅街。メニューには現地の屋台や庶民派料理店のそれが並び、「日帰りの台湾」として、多くのリピーターの驚きと喜びを集める。中でも現在では毎日ひと組は訪れるようになったという在日台湾人からの、「懐かしい!」という言葉。これこそが陳さんへの最大級の賛辞であり、それは日本という国で生きる陳さんの、ある想いを満たすものであった。

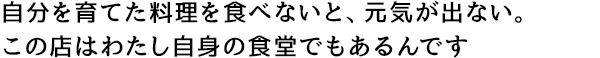 自分を育てた料理を食べないと、元気が出ない。この店はわたし自身の食堂でもあるんです
自分を育てた料理を食べないと、元気が出ない。この店はわたし自身の食堂でもあるんです
 陳ユウテイさん
陳ユウテイさん
このお店は1年半ぐらいになります。プレ・オープンの時期は少しずつ内装を進めながら、クーラーを新調したり、お酒を置く棚を増設したりの出費も多くて大変でしたが、最近はランチも夜もようやく安定してきました。
わたしは「麺線を日本に広めたい」という気持ちだけで突き進んできたんですよ。昼間は大学、夜はバイト、休日は友だちのイベントなどに麺線のケータリングをしたりと自分にできる範囲の実践を積んできたつもりだったんですけど、いざお皿を運ぶ段階になって、お店の経験がまったくないことに気づいてしまって(笑)、このビルのオーナーでもある新妻修さんにはいろんな面で助けてもらいましたね。
ここにお店を出せたのは本当に幸運でした。修さんは何度も台湾に旅行していて、好きなお店がわたしとカブるぐらいに現地の味に通じていたこともありましたし、修さんはこの地下でダンス・スタジオを経営しているんですけど、「レッスンを終えたお客さんがくつろげるようなカフェや軽食屋さんをつくりたい」という考えに、わたしの提案がぴったりと合致して。……修さんは少しでも内装費を浮かせるために大工さんに混ざって作業してくれたり、台湾人のお客さんのために中国語を勉強してくれたり、本当にお世話になっています。
 高い天井が気持ちいい店内。共同経営者の新妻修さんは大のスコッチ党であり、棚にはBARさながらの品添え。ピートの強いものはソーダで割ることで、陳さんの料理のよきパートナーとなる。宜蘭(ぎらん)で生産される台湾ウイスキー「KAVALAN(カバラン)」のコーナーも。
高い天井が気持ちいい店内。共同経営者の新妻修さんは大のスコッチ党であり、棚にはBARさながらの品添え。ピートの強いものはソーダで割ることで、陳さんの料理のよきパートナーとなる。宜蘭(ぎらん)で生産される台湾ウイスキー「KAVALAN(カバラン)」のコーナーも。
「だったらおふたりが並んだ写真を撮りましょう」という取材班に、「いやいやここまで本当に頑張ってきたのは陳さんなので」と謙虚な新妻さん。しかしそのやりとりからは、麺線という(日本人にとっては)未知のメニューをこの地に広めようと苦楽を共にしてきた盟友ならではの信頼関係が見てとれる。
それにしても陳さんの日本語は滑らかだ。訊けば陳さんが日本に住むようになったのは15年ほど前。時代が昭和から平成へと変わってすぐのことだったという。
わたしが生まれる30年以上前に、まずはお母さんが日本にきていたんですけど、わたしを身籠ったことで、出産のために台湾に帰国したんですね。ある事情から、そのときにはもうお父さんはいなくて……わたしは親戚の家を転々としながら台湾の最南端に近い屏東(へいとう)という土地で育てられたんです。当時のお母さんにとってはまだまだ「海外」である日本で、しかも母子家庭という環境でわたしを育てるのは大変だったので、日本での生活の基盤ができるまでは離ればなれでいたんですね。ビザの関係もあって小学生なのにひとりで飛行機に乗って台湾に帰らなくちゃいけなくなったり、中学にあがって日本国籍になるまでは、台湾が50%、日本が50%の安定しない生活が続いていました。うちのお母さんはかなりのスパルタ式なんですよ。だってわたしがまったく日本語ができないのを知っているのに、ふつうの小学校に入学させているんですよ(笑)。やっぱり言葉ができないことからのいじめも受けましたし、泣きながら日本語を勉強して……あの頃は本当に無我夢中でした。
 陳さんの育った屏東の実家を見せていただいた。なんとこのビルの1階から5階が「一軒家」なのだそう。「わたしと、わたしの育ての両親と、その子どもが4人、その子どもにもさらに子どもが生まれているので、みんなでいっしょに暮らしているんです。屏東はきちんと整備された街ですけど、田舎らしさも残っていて、いつ帰っても昔のままの風景が残っている。わたしを子どもに戻してくれる、大切な場所なんです」と陳さん。写真右は台湾の地図と名産品が描かれたペーパーマット。
陳さんの育った屏東の実家を見せていただいた。なんとこのビルの1階から5階が「一軒家」なのだそう。「わたしと、わたしの育ての両親と、その子どもが4人、その子どもにもさらに子どもが生まれているので、みんなでいっしょに暮らしているんです。屏東はきちんと整備された街ですけど、田舎らしさも残っていて、いつ帰っても昔のままの風景が残っている。わたしを子どもに戻してくれる、大切な場所なんです」と陳さん。写真右は台湾の地図と名産品が描かれたペーパーマット。
でも、そんな自分だからこそ、麺線が日本に受け入れられるということに早くから気づけたというのはあります。食べたら絶対に好きになってもらえると確信していましたね。素人のわたしが飲食を始めるのだから、日本ではあまり知られていないもので勝負したいという気持ちもありました。たとえば台湾の観光ガイドに紹介されている小籠包や火鍋やかき氷以外にも、もっとローカルで気軽に食べられる美味しいものというのがたくさんあるんです。
陳さんは麺線に使うモツを丁寧に包丁で切り分けながら、こうも続ける。
日本は素晴らしい国だと思います。でもたまには自分を育てた料理を食べないと、だんだんと元気がなくなってきちゃうんですよね。はい、この店はわたし自身の食堂でもあるんです(笑)。
この「台湾おつまみトマト」なんかはとくに思い出深い味です。生姜と砂糖、あとは梅を粉末にしたものを混ぜ込んだ甘いタレをかけていて、最初はちょっとビックリする人も多いんですけど、日本の中華料理屋さんではまず食べられない味なので、リピートしてくださるお客さんもたくさんいますね。
 「台湾おつまみトマト(蕃茄切盤/ファンジャチエバン)」。ジンジャーシロップや水飴のように甘くコクのあるタレがビールをすすませるという不思議!
「台湾おつまみトマト(蕃茄切盤/ファンジャチエバン)」。ジンジャーシロップや水飴のように甘くコクのあるタレがビールをすすませるという不思議!
特製ダレにキラキラと輝く丸ごとのトマトは開花前のつぼみのように美しく、目にも楽しい。しかしそこに続く「お茶っ葉卵」の形相は、まるで羽化前の恐竜を思わせる迫力で。
これも台湾人にとっては思い出の味です。コンビニにも置いてありますし、大人も子どももみんな大好き。茹で卵にスプーンのお腹で細かいヒビを入れて、それを台湾の高山茶や八角などの香辛料といっしょに煮込むので、こういう模様になるんですね。玉子は冷めるときに味が入っていくので、熱したり冷ましたりを繰り返して、うちでは丸2日ぐらいかけたものを出しています。熱いので注意してくださいね。

 「お茶っ葉卵(茶葉蛋/チャーイェーダン)」。角煮やおでんの卵を連想させつつも、より上品で複雑な薬膳香。ペリペリと殻を剥くのも楽しい!
「お茶っ葉卵(茶葉蛋/チャーイェーダン)」。角煮やおでんの卵を連想させつつも、より上品で複雑な薬膳香。ペリペリと殻を剥くのも楽しい!
台湾はベジタリアンがすごく多いということもあって、「エリンギの唐揚げ」や「蛋餅(ダンピン/台湾式クレープ)」も定番ですね。蛋餅は朝食としてよく食べます。うちでは「豆漿(トウジャン)」という飲み物も出しているので、それとセットで頼まれる人も多いです。豆漿は日本の豆乳に近いものですけど、甘みがもっとさっぱりとしていて、蛋餅の皮にもぴったりなんです。
 「エリンギの唐揚げ」。衣の中にはしっかりと下味をつけられたエリンギのジュースがたっぷり。台湾の塩胡椒に香辛料を加えた特製塩をまぶして。
「エリンギの唐揚げ」。衣の中にはしっかりと下味をつけられたエリンギのジュースがたっぷり。台湾の塩胡椒に香辛料を加えた特製塩をまぶして。
 チーズやハム、コーンなど好みのトッピングで楽しめる「蛋餅(ダンピン/台湾式クレープ)」
チーズやハム、コーンなど好みのトッピングで楽しめる「蛋餅(ダンピン/台湾式クレープ)」
 写真右は蛋餅のトッピングに選んだ「肉鬆(ロウソン)」の缶。豚肉を「でんぶ」のような食感に加工したもので、これも台湾の食卓では定番の「ふりかけ」なのだとか。
写真右は蛋餅のトッピングに選んだ「肉鬆(ロウソン)」の缶。豚肉を「でんぶ」のような食感に加工したもので、これも台湾の食卓では定番の「ふりかけ」なのだとか。
つぎは「ピリ辛魯肉豆腐」です。ランチでは麺線とのハーフ&ハーフでも出している「魯肉飯(ルーローファン)」の具材をアレンジして、お豆腐に乗せたものです。これは台湾にもないわたしのオリジナル料理で、「ちょっとご飯は重いかな」っていう夜の女性のお客さんにも人気ですし、お酒のつまみとしてもよく出てくれますね。
 ピリ辛魯肉豆腐
ピリ辛魯肉豆腐
台湾での勝算ですか? はい、好まれると思います。向こうでは魯肉を茹でた青菜なんかにもかけたりしているので。……ただ、台湾というのはどのお店の店内にも薄いビニール袋というのが常備されていて、それで料理を持ち帰る人がすごく多いので、豆腐だと家に帰るまでにグチャグチャになっちゃうかもしれませんね(笑)。
陳さんの言葉は最高の台湾ガイドでもある。
台湾は有名ブロガーさんの影響力というのがすごく強いので、もし旅行するなら彼らの記事もチェックしてみたほうがいいと思います。グルメやホテルはもちろん、アダルト・グッズの性能を赤裸々に紹介する女性なんかもいて(笑)、お店や企業も彼らをすごく頼りにしている。ブロガーさんが「きのうトイレが壊れた」と書こうものなら、すぐに新しい便器が送られてくるような世界なんですよ(笑)。
あと、向こうでは「夜市(イエスゥ)」という屋台村みたいなところがあるんですけど、日本人がそこに出かけてびっくりするのが、台湾人はそこでお酒を飲む習慣というのがほとんどないということ。夜市はあくまで食べ歩きの場所で、洋服を売ってる出店を見たり、輪投げとか射的とか「スマートボール」みたいな昔のパチンコで遊んだりするようなところなんです。
 写真左は「金門高粱酒」の限定品。53度のハードパンチャー。右はほんのりとした甘さが特徴の台湾産烏龍茶葉。これを煮出して使用した「台湾ウーロンハイ」も最高の食中酒。
写真左は「金門高粱酒」の限定品。53度のハードパンチャー。右はほんのりとした甘さが特徴の台湾産烏龍茶葉。これを煮出して使用した「台湾ウーロンハイ」も最高の食中酒。
飲む場所というのはまたべつにあります。それは看板に「熱炒」という漢字のあるお店(笑)。そこではビールも自分で好きなように取って、空き瓶をテーブルの下にどんどん置いていって、最後に数えてお会計をするようなところなんですね。
こういう食習慣の違いは面白いですよね。わたしも納豆なんかにはかなりビックリさせられましたから(笑)。あと、小さな頃に食べた懐石料理の記憶も鮮明に残ってますね。料理のひとつひとつがすごく小さくて、台湾にも小皿の文化がありますけど、もっともっとカラフルで、なんだか料理のミニチュアみたいだなぁって(笑)。……あと、大人になって改めて感じるのは、日本はなにを食べても塩辛いということ。台湾は風味が強いだけで、実際の塩分というのはそこまで強くないんです。だからわたしの家族なんかがこっちにくると、みんな「しょっぱくて食べられない」っていうんですよ。わたしの料理も塩や醤油は隠し味程度。ほとんどが出汁や香辛料の味なんですね。
 店名の「formosa/フォルモサ」とは、かつてはオランダ領であった台湾の旧称。「台湾ではこの言葉を見かけることがすごく多いんです。ごはん屋さんはもちろん、病院や薬局にも。この言葉はすごく素敵な言葉で、〈美しい〉とか〈麗しい〉という意味。初めて台湾を見たオランダ人が呟いた言葉だと伝えられています。台湾も日本も島国ですから、わたしの店は絶対にこの名前にしたかったんです」
店名の「formosa/フォルモサ」とは、かつてはオランダ領であった台湾の旧称。「台湾ではこの言葉を見かけることがすごく多いんです。ごはん屋さんはもちろん、病院や薬局にも。この言葉はすごく素敵な言葉で、〈美しい〉とか〈麗しい〉という意味。初めて台湾を見たオランダ人が呟いた言葉だと伝えられています。台湾も日本も島国ですから、わたしの店は絶対にこの名前にしたかったんです」
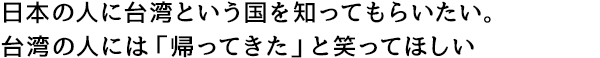 日本の人に台湾という国を知ってもらいたい。台湾の人には「帰ってきた」と笑ってほしい
日本の人に台湾という国を知ってもらいたい。台湾の人には「帰ってきた」と笑ってほしい
確かに陳さんの料理は、その香りや風味こそ独特のものだが、辛味、甘味、酸味などからなる味のレーダーチャートを大きく突き抜けるような要素がなく、尖った部分が舌に触ることがない。新味にあふれ刺激的なのに、どこまでも優しい後味とバランスを保っている。
それは満を持してオーダーした今回のヒトサラ、麺線にも当てはまる。この丸みのある味こそは「呑ん兵衛のために残された究極の締め」でもあって──。
もちろんそこは想定していました(笑)。麺線も専門の屋台で売られているものなので、台湾人はサラッと食べて出るか、テイクアウトして家で食べるかのどちらかなんですけど、この味だったらお酒にもいけますよね。脂肪分のあるものはほとんど入っていないので、ラーメンなんかよりもずっとカロリーが低いし、スープといっしょに食べるので満足感もあると思います。二日酔いの日にもおすすめしますよ(笑)。

 ハーフサイズの麺線(450円)。スープポットで保温されているため、注文後1分で到着。あぁ、こんな店が帰り道にあれば……。
ハーフサイズの麺線(450円)。スープポットで保温されているため、注文後1分で到着。あぁ、こんな店が帰り道にあれば……。
 麺線に使われる麺は塩水を使った特殊な工程で天日干しにされた「紅麺線」と呼ばれるもの。この状態のものを塩抜きして使用するのだそう。「この麺であれば1日中煮込んでも、柔らかさや滑らかさを保ったままスープに溶け出してしまうことがないんです。たまにラーメンのようなものだと思って頼まれるお客さんがいて、〈硬めで〉なんて言われると説明に困っちゃいますけどね(笑)」
麺線に使われる麺は塩水を使った特殊な工程で天日干しにされた「紅麺線」と呼ばれるもの。この状態のものを塩抜きして使用するのだそう。「この麺であれば1日中煮込んでも、柔らかさや滑らかさを保ったままスープに溶け出してしまうことがないんです。たまにラーメンのようなものだと思って頼まれるお客さんがいて、〈硬めで〉なんて言われると説明に困っちゃいますけどね(笑)」
この味に辿り着くまでには紆余曲折ありました。最初はすべて自分ひとりで研究していたんですけど、プレ・オープンを迎えても100%の味にはならなくて、いったんお店を閉めて台湾に帰ったんですね。高雄(カオシュン)にある麺線屋のおばちゃん──すごく大らかで恰幅のいい(笑)──を相手にじっくり交渉を進めて、なんとかレシピを譲ってもらったんです。ただ、食材に関してはまったく同じものにはならないので、そこからまた自分なりの改良を重ねていきました。できることならいつかそのおばちゃんにもわたしの麺線を食べてもらいたいと思っていますね。
 麺線に混ぜ、自分好みの味をつくれる自家製調味料。上から時計回りに、烏酢(ウーツー)、ニンニクのすりおろし、4種の唐辛子による自家製ラー油(発汗必至の辛さ!)。「烏酢は日本の黒酢に近いものですが、もっと酸味が柔らかくて、鰹出汁にもよく合うんです」
麺線に混ぜ、自分好みの味をつくれる自家製調味料。上から時計回りに、烏酢(ウーツー)、ニンニクのすりおろし、4種の唐辛子による自家製ラー油(発汗必至の辛さ!)。「烏酢は日本の黒酢に近いものですが、もっと酸味が柔らかくて、鰹出汁にもよく合うんです」
それにしてもこの味はどうだ。漢方で煮込まれたモツのクニュクニュとした食感、香草のフレッシュな香りが、麺線というスロープに運ばれ喉を滑り落ちる。鰹出汁を効かせたスープは我々の舌にも馴染み深く、これまで日本に根づいていないのが不思議に思えるほどだ。
そう言ってもらえるのはすごくうれしいですね。もっともっと気軽に食べにきてもらえるようになればと思います。うちのお店の熱烈なお客さんは、台湾の文化に興味がある人が多くて、名古屋や福岡、いちばん遠い人は北海道からもきてくださった人もいます。あとは日本で暮らしている台湾人のお客さん。カミングアウトしていないだけで、「実はわたしも……」という人がけっこういらっしゃるんですよ。
だからこそ、もっと店舗を増やしていきたいというのは考えています。すぐにとはいかないと思うけど、そもそもこのお店をやりたいと思った初心というのを大切にしたいんです。それは、日本の人に台湾という国を知ってもらいたいということ。あとは、こっちで暮らす台湾人に、「故郷に帰ってきた。また明日から頑張ろう」と笑ってもらえるような場所をつくりたいということです。日本に夢を持ってやってきた留学生でも、文化の違いに悩まされたり、まだやるべきことがたくさんあるはずなのに寂しくなって帰ってしまうという人がたくさんいると思うんです。そんなとき、フラッと寄ってヤル気を充電できるような「リトル台湾」があちこちにあったらいいなって思うんです。
陳さんの味には希望や信念があり、それが国境を越え人を惹きつける。それもそのはず、「麺線屋 formosa」は、ほかの誰でもない、かつての陳さんが心から欲し、救われるべきであった場所なのだから。
今日の最初にも少しお話しましたけど、実はわたしも、最近までは女子大生だったんです。24歳のときに高卒認定をとって、まったく話の合わない7歳も下の子たちに囲まれながら、なんとか卒業したんです。こっちの子はこないだまで高校生だったわけで、講義中もすごくうるさいから、必死に学費を払いながらの自分はすごく浮いていましたけど、入学当時のわたしには語学しか取り柄がないと思っていたので、通訳になろうと思っていたんですね。……やっぱり自分はどっちつかずの人間じゃないですか。台湾にも日本にも、自分の定位置というものがない。今後も長く日本で暮らしていくためにも、どこかで台湾と日本を結ぶ仕事をしていないと、自分というものが消えてしまう気がしていたんです。
だからいまは、こうした料理を通じて台湾を伝えられるようになったことがうれしくてしかたがないし、朝から晩まで働き詰めですけど、不思議と疲れるということがないんです。
あまり日本語も喋れないのにこんな場所まで迷いながら、わたしの店を探しにきてくれる留学生なんかの顔を見ると、自分のやっていることに誇りを持てるんです。そんなときこそ、これまでの人生に無駄はなかったと思えるし、これまでの自分を好きになれる気がするんですよ。


麺線屋 formosa
神奈川県川崎市高津区二子2-15-7
050-5847-7248
営業時間:1:30~15:00/18:00~24:00
定休日:火曜日
| 前の記事 世田谷区若林「唐木屋」 坂本義一さんの「唐木屋のなか」 |
次の記事 世田谷区北沢「sunaga」 須永祐司さんの「豚足・豚耳・豚ほほ肉の メンチカツ」 |