 グラスを傾けつつ嗜みたい、酒香るエッセイにして、ヒトとヒトサラ流のカルチャー・ガイド。ミュージシャンや小説家、BARの店主や映画人。街の粋人たちに「読むヒトサラ」をお願いしました。
グラスを傾けつつ嗜みたい、酒香るエッセイにして、ヒトとヒトサラ流のカルチャー・ガイド。ミュージシャンや小説家、BARの店主や映画人。街の粋人たちに「読むヒトサラ」をお願いしました。

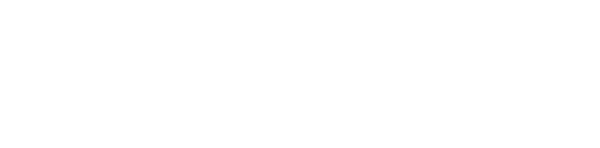 サイドオーダーズ06 / TEXT+PHOTO:南澤孝見 / 2014.10.22 BARのシーンをコレクトすること──南澤孝見
サイドオーダーズ06 / TEXT+PHOTO:南澤孝見 / 2014.10.22 BARのシーンをコレクトすること──南澤孝見
映画に出てくるバーカウンターのシーンが好きで、そんなシーンを切り取っては、なんとなく集める癖がある。
僕の親父は、ニューヨークに会社を構えるダイヤモンドの貿易商だった。葉巻やブランデーを日常の友とし、銀座に自分のBARを持ったりする、派手好みな男だった。そんな環境のせいか、「大人とはBARに行く生物である」と幼い頃から刷り込まれた。「15歳になったらBARで注文する自分の酒を決めろ」と言われて育った。
もちろん僕自身は、15歳になってもBARになど行くワケもなく、映画に出てくるBARのシーンを観ては、勝手な妄想を膨らませるのだった。
だんだんと妄想は加熱した。高校の文化祭では毎年いろいろな趣向をこらしたBAR(ノンアルコールだけど)を出店したし、芸大では卒業制作がわりにBARを出店したりもしたが、それでも実際のライフスタイルではBARなど縁がなく(美大生は小汚い居酒屋がクールとされていた)、好奇心が実際の行動と結びつくことのないシャイで妄想派だった僕は、いつしか自分の「いきつけ」というものを、映画や小説の中に探すようになったのだった。
そうこうして大人になった現在の僕は、もうシャイでもないし、BARに行ったり、趣味が高じて多くのBARのデザインやプロデュースを仕事にしたりさえしているが(写真は町田「WINDSOR」の内装だ)、今でもやっぱり、映画や小説の中のBARは特別である。
さて、僕はウイスキーが好きだ。ウイスキーは、BARの照明や環境にあってこそ美味しいものであると思い込んでいるので、そのほかの場所ではまず飲むこともないのだが、これも完全にBARシーンの影響である。主人公たちの傾けるグラス。氷の音。溶けていく琥珀色。
SF作家の星新一の小説は、バーカウンターに座る主人公が、グラスを重ねる、そんなシーンから始まるものが多い。心に隙が生じるバーカウンターの魔法を借りて、いかがわしい人間や逸話が侵入してくるのだ。日常の結界が破れ、異界の扉が開く。
人はそもそも異界を求めてBARに近づくのだと思う。異界への入り口は、隣に座った異性であるのはご承知のとおりである。
映画においても、BARカウンターで男女が出会うシーンは鑑賞の醍醐味である。なにかしらの傷をもった主人公に絡みつく、異性の目配せや駆け引きのあれこれ。
チャールズ・ブコウスキー原作の傑作BAR映画『バーフライ』では、共に傷ついた男女、ミッキー・ロークとフェイ・ダナウェイが出会うシーンが好きだ。カウンターで声をかけられた女というものは、はしゃいでしまったら台なしである。できる限りそっけなくてはならない。視線をグラスから離さずに話してくれれば、なお素晴らしい。もっともこの映画のフェイに至っては、そっけないを遥かに超え、「虚脱」の域だが。
名作『アパートの鍵貸します』のBARシーンも印象的だ。女とうまくいかずに茫然自失のジャック・レモンが、ひとりマティーニを頼んでは、オリーブのピン(串)を、カウンターの上に何本も並べている。遠くの席の女がストローで吹き矢をつくり、ジャックに紙筒を飛ばし続けるが気づかない。カウンターの吹き矢というのは、女性からのアプローチとしてはかなり斬新である。その後、オンナはジャックに近づき、「彼氏がキューバに革命しに行っちゃってひとりぼっちなの」と誘い、最後はふたり、泥酔しながら閉店までチークダンス(フェードアウト)。
また、BARというものは、よそ者にとっては戦場である。西部劇においてもBARのシーンは切っても切れないものだが、ジョン・ランディスの喜劇『サボテン・ブラザーズ』のそれは、映画を愛する者の深い慈愛に満ちた傑作シーンなので、ぜひご鑑賞あれ。これだけは何度観てもお腹が痛い。
よそ者設定は大体ハズレがないのだが、ジョン・カサヴェテスとピーター・フォークがただ逃げ惑うだけの映画『マイキー&ニッキー』では、彼らが黒人専門?のBARに逃げ込み、大立ち回りするシーンが素晴らしい。アメリカでこのネタはなかなか勇気がいるのではないだろうか。
また、『ポリスアカデミー』では、「ブルーオイスター」というハードゲイのBARに警官が入ってしまい大モテするシーンがあるが、よそ者であってホンモノ(の格好)という馬鹿な設定、これが大受けした理由であろう。テレビ放映時には水野晴雄センセイが解説されていたのもサイコーであった。
日本映画では、岡本喜八の『江分利満氏の優雅な生活』によいシーンが多い。ほどよいサイズ感の店をハシゴ酒するサラリーマンの小林桂樹が、結構ディープな内容の話をしていくのだが、昭和30年代のBARを追体験するにはうってつけだ。ウイスキーもグイグイ飲んでいてうまそうだ。
日本のスナックや小料理屋を、BARと定義するかどうかは難しいところだが、「カウンター越しのドラマ」としては、やはり秀逸なものが多い。
バーテンダーというものはあくまで脇役、しかしそれが「オカミサン」になると突如主役級に変貌する。中でも映画『駅 STATION』での高倉健と倍賞千恵子のやり取りは絶妙だ。大晦日の晩、客もいないカウンターだけの小料理屋にガラリと戸を開け入ってくる健サン。出会ったばかりのふたりは身の上話とともに好意を寄せ合い、やがてカウンターに並んでいっしょに杯を交わしだす。熱燗と、テレビに映る紅白歌合戦。流れる唄は都はるみ。様式美の極致である。
バーカウンターでの出会いというものは、多くの場合、安っぽいナンパであるか、当たり障りのない暇つぶしの会話である。それが映画の中では、一夜のアバンチュールに発展したり、人生を変える奇跡の出会いになり得るのだから、展開としては実に便利。それゆえ慎重に扱わねばならず、印象的なシーンになりえることが多いのだと思う。
また、設計者や運営者が相当な間抜けでない限り、BARの照明は女性を美しく見せるようにできているもの。ヒロインの劇的な登場シーンには、うってつけの空間なのだ。あまりにも有名な『パリ、テキサス』という映画、ナスターシャ・キンスキーが振り向くシーンは、それだけでこの映画を名作にしてしまったほどだ。
そろそろ好きなコレクションをあげ連ねるのも、ここでおしまいにしようと思う。
もし貴方が素敵なBARシーンを見つけたら、どうかぜひ、僕に教えてくださいな。
SIDE ORDERS :
・『バーフライ』(1987)
・『アパートの鍵貸します』(1960)
・『駅 STATION』(1981)
・『江分利満氏の優雅な生活』(1963)
| 前の記事 サイダーが導くアウトサイダー音楽航路 ──飯島直樹 |
次の記事 『深夜食堂』を撮り続けてきて思う 二、三の事柄──松岡錠司 |

